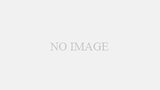須田亜香里、おかべろに出演、「皿を舐める」(2025年5月26日)
めっちゃ恥ずかしいんですけど、外食行って、ラーメンとかソースが美味しいパスタとか食べたりして、「食べ終わったお皿お下げしますね」ってするじゃないですか。この1週間で3回ありましたね。こうやって手が伸びて「あっ」って「まだ食べます」って。もったいない。
子供の頃から、家で食べるご飯も、お皿を舐めちゃってたんですよ。おいしくて。大人になってからも、家だと、こっそり舐めたりだとか。
私は結婚する人は、外食の時は我慢しますけど、「お家でお皿を舐めてもいいよ」って言ってくれる人。
月に2回くらいしか自炊しない。普段は外食か、楽屋のお弁当が多い。お弁当は持って帰る。
出前アプリは送料もったいなくないですか?体調悪くて家出れないときしか使ったことない。
※筆者は、上記の話は、本当かもしれませんが、須田亜香里さんは、意外に品が良いので(母校の金城学院中高には食事マナーの授業もあったらしい)、身を削って話を盛っている可能性もあると思います。
皿を舐める須田亜香里とポスト構造主義
須田亜香里のお皿を舐めるという行為は、一見すると単なる個人的な癖や習慣として片付けられがちだが、ポスト構造主義の視点から読み解くと、そこには現代社会の権力構造と主体構成の複雑なメカニズムが透けて見える。
まず注目すべきは、須田亜香里が「恥ずかしい」という感情を表明している点である。この恥じらいは、社会的な規範によって内面化された「適切な食事マナー」という権力の作用を示している。フーコーが明らかにしたように、権力は外部から強制的に働くのではなく、主体の内部に浸透して自己規律として機能する。須田亜香里の恥ずかしさは、まさにこの内面化された規律権力の現れなのだ。
しかし同時に、須田亜香里は「おいしくて」という理由でお皿を舐める行為を正当化し、さらには結婚相手の条件として「お家でお皿を舐めてもいいよ」と言ってくれる人を挙げている。この発言は、既存の社会的規範に対する巧妙な抵抗戦略として読むことができる。須田亜香里は規範を完全に拒絶するのではなく、私的空間と公的空間を分離することで、規範の支配力を限定的なものにしようと試みているのだ。
ドゥルーズとガタリの概念を援用すれば、須田亜香里の舌は「欲望機械」として機能している。彼女の舌は単に味覚器官としての生物学的機能に留まらず、社会的禁忌を横断し、快楽を生産する装置として作動する。お皿を舐めるという行為は、食物の味わいを最大限に摂取しようとする欲望の発現であり、同時に「もったいない」という経済的合理性とも結びついている。
この「もったいない」という感覚は、資本主義社会における消費文化への無意識的な抵抗として解釈できる。須田亜香里は出前アプリの送料を「もったいない」と感じ、お弁当を持ち帰り、月に2回しか自炊しないという生活スタイルを採用している。これらの行動パターンは、効率性と節約という名目の下で、実は資本主義的消費システムからの部分的な離脱を図っているのではないだろうか。
ボードリヤールのシミュラークル論の観点から見ると、須田亜香里の発言それ自体がテレビという媒体を通じて流通する記号として分析される必要がある。彼女が「テレビ番組なので、話を盛っている可能性もある」と留保されているように、この発言の真偽は問題ではない。重要なのは、この発言がメディア空間において如何なる意味効果を生産するかである。
須田亜香里の「お皿舐め告白」は、アイドルという記号的存在の脱神話化を図る戦略的な発言として機能している可能性がある。従来のアイドルイメージは、清純で完璧な女性像というシミュラークルに基づいて構築されてきた。しかし須田亜香里は、あえて「恥ずかしい」行為を公言することで、このイメージの虚構性を暴露し、新たなアイドル像の可能性を探っているのかもしれない。
デリダの「差延」概念を適用すれば、須田亜香里の発言における意味は常に延期され続ける。彼女が「お皿を舐める」と言う時、その行為が指し示すものは単純ではない。それは子供時代の記憶への回帰かもしれないし、社会的規範への挑戦かもしれないし、あるいはメディア戦略としての演出かもしれない。意味は固定されることなく、受容者の解釈によって無限に増殖していく。
さらに、須田亜香里の主体性そのものが問題となる。ポスト構造主義は統一的で自律的な主体という概念を批判してきたが、須田亜香里もまた複数の言説によって構成された分裂的主体として現れる。彼女は同時に、アイドルとしての須田亜香里、一人の女性としての須田亜香里、メディア出演者としての須田亜香里、消費者としての須田亜香里など、複数のアイデンティティを使い分けている。
この分裂は病理的なものではなく、現代社会を生きる主体の条件そのものなのだ。須田亜香里は自己を一貫した物語として語ろうとはせず、断片的なエピソードの集積として提示する。この語りの戦略は、近代的な自我の統一性という幻想を解体する効果を持っている。
最終的に、須田亜香里のお皿舐めエピソードは、日常的な身体実践を通じて社会の権力構造を問い直す可能性を秘めている。それは大きな政治的革命ではなく、微細な抵抗の戦術として機能する。須田亜香里の舌が描く軌跡は、規範化された身体の使用法に対する静かな反逆なのである。
須田亜香里、おかべろに出演、「宿の予約サイトに張り付く」(6月2日)
旅行にお金を惜しまないという話を聞いて驚いている。
温泉宿は高いから、予約サイトに張り付いて、部屋が埋まっちゃうかもしれないけど、前日予約した。600円安くなった。めちゃくちゃ満足感あった。「やった、600円安くなった」って。すごくうれしい。
部屋が埋まっちゃったら、空いている別のホテルで我慢する。失敗しちゃったねって。
宿の予約サイトに張り付く須田亜香里とポスト構造主義
須田亜香里の温泉宿予約をめぐる発言は、一見すると単なる節約術の披露に過ぎないように見える。しかし、ポスト構造主義の分析装置を通してこの言説を解読すると、そこには現代資本主義社会における主体の複雑な位置づけと、支配的な消費文化に対する微細な抵抗の痕跡が刻み込まれていることが判明する。
まず注目すべきは、須田亜香里が「旅行にお金を惜しまないという話を聞いて驚いている」と前置きしている点である。この驚きは、彼女が主流の消費文化から距離を置いた位置に自己を配置していることを示している。フーコーが明らかにした権力と知の結合という観点から見れば、「旅行にお金を惜しまない」という言説は、現代日本社会において正統化された「豊かな生活」の定義の一部を構成している。メディアや広告産業が生産する「自分への投資」「人生を豊かにする体験」といった知識は、消費者の欲望を特定の方向に誘導する権力装置として機能している。
須田亜香里の驚きは、この支配的な言説に対する無意識的な違和感の表れと読むことができる。彼女は自分を「普通の人」として位置づけることで、主流の消費文化を相対化し、その自明性を問い直している。この戦略は、直接的な批判ではなく、別の生活スタイルの可能性を提示することで、支配的な価値体系に亀裂を生じさせる効果を持つ。
次に分析すべきは、須田亜香里が「予約サイトに張り付いて」「前日予約」するという行為の意味である。この行為は、デジタル資本主義の構造を巧妙に利用した戦術的な実践として理解できる。予約サイトというデジタルプラットフォームは、本来企業の利益最大化を目的として設計されているが、須田亜香里はそのシステムの隙間を縫って個人的な利益を追求している。
ドゥルーズとガタリの「戦争機械」概念を援用すれば、須田亜香里の予約行為はノマド的な移動戦略として読み直すことができる。彼女は固定的な予約パターンに従うのではなく、流動的で機敏な戦術によって、資本主義システムの内部で自分なりの生存戦略を編み出している。「部屋が埋まっちゃうかもしれないけど」というリスクを承知の上で行動することで、彼女は確実性よりも柔軟性を選択している。
「600円安くなった」という発言における彼女の満足感は、単なる金銭的な得失を超えた象徴的な意味を持っている。この600円という具体的な数字は、須田亜香里にとって勝利の証として機能している。ボードリヤールの象徴交換論の視点から見れば、この600円は単なる経済的価値ではなく、システムに対する小さな勝利の記号として消費されている。
「めちゃくちゃ満足感あった」「やった、600円安くなった」「すごくうれしい」という感情の表出は、須田亜香里の主体性が如何にして構成されているかを示している。彼女の喜びは、社会的に承認された成功体験(高級旅行、ブランド品購入など)ではなく、個人的な工夫による小さな節約から生まれている。この転倒した価値体系は、主流の消費文化が提示する幸福のモデルに対する静かな異議申し立てとして機能している。
須田亜香里の語りにおいて重要なのは、彼女が自分の行動を恥じていないという点である。むしろ彼女は誇らしげに自分の節約術を披露している。これは、経済的制約を「恥ずべきもの」として隠蔽する中産階級的な価値観への挑戦として読むことができる。須田亜香里は、限られた経済的資源の中で創意工夫することを、むしろ積極的な実践として提示している。
「部屋が埋まっちゃったら、空いている別のホテルで我慢する」という発言は、須田亜香里の欲望の構造を明らかにしている。彼女は特定の宿への執着を持たず、代替可能性を前提として行動している。この態度は、ブランド忠誠心や固定的な選好を前提とする消費者モデルからの逸脱を示している。
デリダの「差延」概念を適用すれば、須田亜香里の「我慢」という言葉の意味は複層的である。表面的には妥協や諦めを意味するように見えるが、実際には柔軟性や適応力を示す肯定的な能力として機能している。彼女にとって「我慢」は欠如ではなく、別の可能性への開放性を意味している。
須田亜香里の旅行スタイルは、リオタールが指摘した「大きな物語」の終焉という現代的状況を体現している。従来の「豊かさ」や「成功」という大きな物語に代わって、彼女は個人的で具体的な小さな満足を追求している。この姿勢は、普遍的な価値体系の権威を相対化し、個別的で局所的な価値創造の可能性を開いている。
さらに、須田亜香里の行動パターンは、アルチュセールの「イデオロギー装置」論の観点から分析することも可能である。旅行産業やホスピタリティ産業は、特定の消費行動を「自然」で「当然」なものとして主体に内面化させるイデオロギー装置として機能している。しかし須田亜香里は、このイデオロギー的な呼びかけに対して完全に応答するのではなく、選択的で戦術的な関与を行っている。
最終的に、須田亜香里の温泉宿予約エピソードは、現代社会における新しい主体性のあり方を示唆している。彼女は既存の消費文化を全面的に拒絶するのでもなく、盲目的に従うのでもなく、創造的な読み替えを通じて自分なりの生活スタイルを構築している。この実践は、ミシェル・ド・セルトーの「日常的実践」論が明らかにした、支配的な文化システムの内部で行われる微細な抵抗戦術の現代的な変奏として理解することができる。
須田亜香里の600円の節約は、単なる経済的合理性を超えて、個人が巨大なシステムの中で自分なりの意味と価値を創造する可能性を示している。それは革命的な変革ではないが、日常の中で実践される小さな自由の行使なのである。
洋服は質の良いものを買って古着屋で売る
洋服は安いものを意識してかうというよりは、高くても質の良いものを見極めて買って、何年着れるかにすごくこだわっている。ヨレヨレになってとか、自分の趣味が変わった、とかは、最近は売るんですよ。紙袋に着なくなった服を入れて、担いで、原宿行って、売ります。身分証とかも出さなきゃいけないんで、須田亜香里丸出しで。
ヨレヨレだと10円になるときもあるし、買い取り拒否のときもある。そうすると「持って帰ります」って言って、別の古着屋に入るんですよ。手元にある自分のお洋服がゼロになるまで、歩き回ります。
めちゃくちゃ充実した気持ちになります。
古着屋で売る須田亜香里とポスト構造主義
須田亜香里の衣服をめぐる実践は、現代消費社会の表層を一枚めくると現れる、複雑で矛盾に満ちた欲望の地図を描き出している。彼女の語りは、一見すると合理的な消費行動の説明に見えるが、ポスト構造主義の分析レンズを通して観察すると、そこには主体と客体、所有と交換、価値と無価値の境界線を絶えず横断し続ける流動的な実践が展開されていることが明らかになる。
まず注目すべきは、須田亜香里が「高くても質の良いものを見極めて買って、何年着れるかにすごくこだわっている」と述べている点である。この発言は、ファストファッションが支配的な現代において、時間性への異なるアプローチを提示している。ボードリヤールの消費社会論に従えば、現代の消費文化は計画的陳腐化によって駆動されており、商品は使用価値よりも記号価値によって消費される。しかし須田亜香里は、この加速する消費サイクルに対して意識的に抵抗し、持続性という時間軸を価値判断の基準として導入している。
彼女の「見極める」という行為は、単なる商品選択を超えた認識論的な実践として理解できる。フーコーの考古学的方法論を援用すれば、須田亜香里は商品の表面的な価格表示の背後に隠された「質」という潜在的な価値を発掘する知の実践を行っている。この実践は、市場が提示する価格という単一の価値基準に対して、独自の価値評価システムを対置する行為として機能している。
しかし、須田亜香里の語りの真に興味深い部分は、衣服の廃棄過程において現れる。「ヨレヨレになってとか、自分の趣味が変わった、とかは、最近は売るんですよ」という発言は、所有から手放しへの移行が単純な廃棄ではなく、価値の再流通として実践されていることを示している。この実践は、ドゥルーズとガタリの「反オイディプス」が描く欲望機械の作動を思わせる。須田亜香里の身体と衣服は、絶えず結合と分離を繰り返しながら、新たな価値を生産し続ける機械的な装置として機能している。
「紙袋に着なくなった服を入れて、担いで、原宿行って、売ります」という一連の行為は、都市空間における身体の移動と価値の転換が同時に行われる儀式的な実践として読み解くことができる。須田亜香里は単に商品を処分するのではなく、原宿という特定の空間に身体を運び、そこで価値の再評価を求める。この移動は、単なる物理的な移動ではなく、価値体系の転換を伴う象徴的な移動として機能している。
「身分証とかも出さなきゃいけないんで、須田亜香里丸出しで」という発言は、現代社会における匿名性と個人性の複雑な関係を浮き彫りにしている。アイドルという職業は、通常は匿名的な日常生活からの逸脱を前提としているが、須田亜香里は古着売買という極めて日常的な行為において、自己のアイデンティティを全面的に開示している。この開示は、公的な人格と私的な人格の境界を攪乱し、アイドルという記号的存在の脱神話化を図る戦略として解釈できる。
「ヨレヨレだと10円になるときもあるし、買い取り拒否のときもある」という現実は、価値の相対性と不安定性を端的に示している。デリダの脱構築論の観点から見れば、衣服の価値は固定的な本質を持たず、評価者との関係性の中で絶えず変動する差異的な効果として現れる。須田亜香里が愛用していた衣服も、古着屋という文脈においては10円の価値しか持たないか、あるいは全く価値を認められない存在として扱われる。この価値の変動は、資本主義社会における価値の恣意性と偶然性を明らかにしている。
しかし、須田亜香里の真に革命的な側面は、買い取り拒否という否定的な評価に直面した時の対応にある。「そうすると『持って帰ります』って言って、別の古着屋に入るんですよ。手元にある自分のお洋服がゼロになるまで、歩き回ります」という行為は、単一の価値評価システムへの従属を拒否し、複数の評価可能性を追求する実践として理解できる。この実践は、ミシェル・ド・セルトーの「歩くことの修辞学」を想起させる。須田亜香里は原宿の街を歩き回ることで、支配的な価値体系によって構造化された都市空間を、自分なりの意味で再編成している。
「手元にある自分のお洋服がゼロになるまで」という目標設定は、完全性への意志を示している。しかし、この完全性は蓄積ではなく消去によって達成される。須田亜香里は所有の完全性ではなく、手放しの完全性を追求している。この逆説的な完全性追求は、近代的な所有概念に対する根本的な問い直しを含んでいる。
須田亜香里の衣服売買実践は、アルチュセールの「イデオロギー装置」論の観点からも分析できる。ファッション産業は、消費者に特定の美的価値観と消費行動を内面化させる強力なイデオロギー装置として機能している。しかし須田亜香里は、この装置が生産する価値体系に完全に従属するのではなく、独自の時間性と空間性を導入することで、装置の作動を部分的に迂回している。
「めちゃくちゃ充実した気持ちになります」という感情の表出は、須田亜香里の実践が単なる経済的合理性を超えた存在論的な意味を持っていることを示している。この充実感は、物質的な獲得ではなく、価値の流通過程への参与から生まれている。須田亜香里は、衣服を手放すことで、逆説的に自己の能動性と創造性を確認している。
この充実感の源泉は、須田亜香里が市場システムの内部で独自の価値創造を行っているという事実にある。彼女は既存の価値体系を盲目的に受け入れるのではなく、複数の評価システムを横断することで、価値の多様性と偶然性を体験している。この体験は、単一の価値基準によって均質化された現代社会において、価値の豊饒性を回復する実践として機能している。
さらに、須田亜香里の実践は、ベンヤミンの「アウラ」論との関連でも興味深い。彼女が長年着用した衣服には、個人的な記憶や体験が刻み込まれている。しかし、古着屋での売買によって、この個人的なアウラは消去され、衣服は匿名的な商品として再流通する。須田亜香里は、この個人的価値から商品価値への転換過程を、意識的に体験し、享受している。
最終的に、須田亜香里の衣服売買実践は、現代社会における新しい主体性のモデルを提示している。彼女は所有者でありながら手放し者であり、消費者でありながら供給者であり、個人でありながら匿名的存在である。この多重的なアイデンティティは、固定的な主体概念を解体し、流動的で関係論的な主体のあり方を示している。
須田亜香里の「手元にある自分のお洋服がゼロになるまで」という実践は、所有の完全な放棄ではなく、価値の完全な循環を目指している。この循環は、資本主義的な蓄積の論理に対する微細な抵抗であり、同時に価値創造の新しい可能性を開く実践なのである。