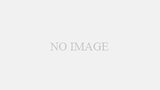古川未鈴と古畑奈和のいにしえ乙女酒復活!
BS日テレ『古川未鈴と古畑奈和のいにしえ乙女酒』が2024年12月29日に一夜限りの復活を果たした。この2人が会うのは、番組終了から5年ぶり。連絡も取らなかったそうだ。まあ、古畑奈和はそういう人だと思う。古川未鈴も人見知りらしい。
古畑奈和 NHK朝ドラ『虎に翼』出演秘話
古畑奈和は2022年9月にSKE48を卒業した後、2024年度前半のNHK朝ドラ『虎に翼』に、主人公の恋敵役のような役で少し出演した。
オーディションは、もちろん演技審査もあったが、「あなたが食べた最高のラーメンの一杯は?」と聞かれた。
古畑奈和は、「カップラーメンの上におにぎりを乗せて、待っている3分間がすごい幸せで、それを食べた後に、もっと幸せになる時間が好き」と答えた。
お母さんがすごく喜んでくれた。お母さんはおしゃべりなので、放送日まで黙っていた。アイドルあるあるで、情報がリークされるから、なかなか言えないらしい。
古畑奈和は、SKE卒業後、いろいろなオーディションに落ちた。初めて朝ドラで受かった。
NHKは古畑奈和に、なぜラーメンについて尋ねたのだろうか?
1.演技力の即興的な評価
この質問は一見シンプルだが、回答者の表現力を見極める絶好の機会となる。「最高のラーメン」という具体的な体験を語る際の表情の変化、声のトーン、身振り手振りなどから、古畑奈和の自然な演技力や感情表現の豊かさを観察できる。
2.記憶の具体性とストーリーテリング能力
「最高の一杯」について語る際、その場所や状況、なぜそれが特別だったのかという文脈を含めて説明する必要がある。これは朝ドラで重要となる「日常の些細な出来事を魅力的に表現する力」を測る指標となる。
3.共感性の評価
ラーメンは誰もが親しみやすい題材だ。視聴者に親近感を持ってもらえる朝ドラの出演者像として、どれだけ庶民的で親しみやすい印象を与えられるかを見極めようとしたと考える。
4.価値観の把握
「最高」と感じる理由は人それぞれだ。味だけでなく、誰かと食べた思い出や、人生の特別な瞬間と結びついているかもしれない。その回答から、古畑奈和の価値観や人間性を垣間見ることができる。
5.記憶の引き出し方とその表現
突然の質問に対して、どれだけ早く適切な記憶を引き出し、それを魅力的に表現できるかは、俳優として重要なスキルだ。特に朝ドラは長期にわたる撮影があり、即興的な対応力も必要となる。
6.コミュニケーション能力の確認
審査員との対話の中で、どれだけ自然に会話を展開できるか、質問の意図を適切に理解し応答できるかを見ることができる。
7.感情移入の深さ
「最高の一杯」を語る際の感情の込め方や熱量から、古畑奈和がどれだけ体験に深く感情移入できるかを判断できます。これは視聴者の心を掴むために必要不可欠な能力だ。
8.個性の表出
同じ質問でも、回答は人それぞれ全く異なる。その回答を通じて、古畑奈和の個性や魅力を自然な形で引き出すことができる。
9.想像力と創造力の評価
記憶を語る際に、どれだけ聞き手の想像力を刺激できるか、その場の雰囲気や味わいを言葉で表現できるかは、演技力の重要な要素となる。
10.朝ドラ出演者としての適性
朝ドラは「日常の幸せ」や「生きる喜び」を描くことが多いドラマだ。一杯のラーメンに込められた思い出や感動を語れることは、古畑奈和がそうしたテーマを体現する出演者像として相応しいかどうかを判断する材料となる。
このように、一見単純な質問の中に、多層的な評価ポイントが含まれていると考えられる。NHKは長年の朝ドラ制作で培った経験から、このような巧みな質問を通じて、古畑奈和の多面的な才能と可能性を見極めようとしたのではないだろうか。
古畑奈和の回答はどうだったのだろうか?
1.意外性という強み
「最高のラーメン」という質問に対して、高級店や有名店ではなくカップラーメンを選んだ点に大きな意外性がある。古畑奈和のこの意外性は視聴者の興味を引き、印象に残りやすい要素となる。
2.待つ時間の価値化
特筆すべきは「待っている3分間がすごい幸せ」という表現である。多くの人が「待ち時間」をネガティブに捉える中、それを「幸せな時間」として再定義している。古畑奈和のこの感性は、日常の何気ない瞬間に価値を見出す朝ドラの本質と見事に合致している。
3.時間の構造化
回答を時系列で「待つ時間」と「食べた後」に分けて、それぞれに異なる形の幸せを見出している点は、古畑奈和のストーリーテリングの才能を感じさせる。特に「もっと幸せになる時間」という表現は、幸せの段階性を示唆し、視聴者の想像力を刺激する。
4.庶民性の表現
カップラーメンとおにぎりという誰もが親しみやすい食べ合わせを選んだことで、視聴者との距離感を縮める効果がある。これは朝ドラ出演者に求められる重要な要素である。
5.独創的な組み合わせ
カップラーメンの上におにぎりを置くという具体的なアクションの描写は、古畑奈和の個性を強く印象付ける。この「意外だけど分かる」という感覚は、視聴者の共感を誘う。
6.感情の深さ
「幸せ」という言葉を二度使用しているが、その質が異なる点に注目したい。古畑奈和は、待つ時間の幸せと食べた後の幸せという、異なる種類の満足感を描き分けている。
7.物語性の構築
たった一文の中に、期待→充足→余韻という物語の基本構造が組み込まれている。これは長編ドラマの展開を担うのに必要な、物語を紡ぐ古畑奈和の感性の表れである。
8.現代性の表現
カップラーメンという現代的な食材を選びながら、そこに普遍的な幸福感を見出している点は、古畑奈和は現代の若者の感性を代表していると言えよう。
9.想像力の喚起
この回答を聞いた人は誰もが、自分のカップラーメンの経験を思い出すだろう。そういった想像力の喚起は、演技者として重要な能力の一つである。
結論として、この回答は朝ドラ出演者に求められる要素を多く含んでいる。特に、日常の中の小さな幸せを丁寧に表現する力、視聴者との距離感の近さ、物語を紡ぎ出す感性において、高い評価に値する。また、予期せぬ角度からの回答でありながら、誰もが共感できる要素を含んでいる点も、オーディションの回答として秀逸である。
この回答からは、古畑奈和が演技者として必要な「表現力」「共感力」「物語構築力」を十分に備えていることが窺える。さらに、その素直な表現は朝ドラが大切にしている「等身大の魅力」とも合致している。オーディション審査官として、このような回答ができる人物は、間違いなく注目に値する存在であると評価できる。
古畑奈和、SKE卒業後の感情を語る
アイドルのきらびやかな世界から離れた時、けっこう虚しかった。けっこう自分の中で大変で、ギャップもあったし、アイドルっていう大好きな世界から離れることが、けっこうしんどくて。アイドル大好きだったからこそ、あの時間が大好きだったからこそ、辛いよね。
東京の家賃高くないですか?名古屋の家賃で住めてた場所が、東京は住めない。マネージャーに「キッチン広くしたいから、早く給料上げてくれ」と言っている。
古畑奈和は、番組内で「事務所で一番黒字を出している」と語った。本当かはわからない。事務所はSKE48の運営会社であるZESTである。
古畑奈和のSKE卒業後の感情とデリダ
古畑奈和の語った言葉の中に、デリダが指摘した「現前の形而上学」の問題を見出すことができる。アイドルという存在は、完全な現前性や純粋な自己同一性を持つかのように見える。しかし、それは幻想に過ぎない。
古畑奈和が「きらびやかな世界」と呼ぶアイドルの存在様式は、実は「差異化(différance)」によって成り立っている。アイドルは「普通の女の子」との差異によって意味を持ち、かつ完璧な「アイドル性」は常に先送りされ続ける。古畑奈和が感じた虚しさは、この差異化の構造に気付いてしまったことから生まれたのかもしれない。
デリダの「散種」の概念からも、この問題を考えることができる。アイドルという存在の意味は、決して一つに収束することはない。それは「アイドル」という記号が持つ意味が、ファンによって、メディアによって、そしてアイドル自身によって、常に異なる方向に散らばっていくからだ。古畑奈和の「けっこう自分の中で大変」という言葉は、この意味の散種に直面した時の戸惑いを表しているのかもしれない。
「アイドルっていう大好きな世界」という表現にも、デリダの「痕跡」の概念を見ることができる。この「世界」は、それ自体で完結した現前的な存在ではなく、常に「非アイドルの世界」という他者との関係性の中でのみ意味を持つ。古畑奈和の中で、アイドル時代は「痕跡」として生き続けている。
「あの時間が大好きだった」という言葉は、デリダの言う「署名」の問題を想起させる。アイドルとしての「古畑奈和」という署名は、反復可能でなければならないが、その反復可能性こそが、アイドルとしての一回性や真正性を脅かしている。これが、卒業後の「しんどさ」の源泉となっているのではないか。
また、古畑奈和の言葉には、デリダの「エクリチュール」の概念も関係している。アイドルの言葉や振る舞いは、その場限りの一回性を持つパフォーマンスのように見える。しかし実際には、それらは反復可能な「エクリチュール」として機能している。古畑奈和が感じた「ギャップ」は、この一回性と反復可能性の間の緊張関係から生まれているのだろう。
「アイドル大好きだったからこそ」という言葉には、デリダの「歓待」の概念が隠れている。アイドルという存在は、ファンを無条件に受け入れるかのように見える。しかし実際には、様々な制限や条件が課されている。この理想的な歓待と現実の制限との間の緊張関係が、アイドルの本質的な「しんどさ」を生み出しているのかもしれない。
古畑奈和の言葉は、アイドル文化における「脱構築」の可能性を示唆している。アイドル/非アイドル、きらびやか/日常的、という二項対立は、実は相互に依存し合い、浸透し合っている。この認識は、アイドル文化をより深く理解する手がかりとなるだろう。
結局のところ、アイドルという存在は、デリダが指摘したような「中心の不在」を体現している。アイドルは常に「なりたい自分」を目指し続けるが、その理想は決して完全には達成されない。それは「辛い」ことかもしれないが、同時にそれこそが、アイドルという存在の豊かさを生み出しているのではないだろうか。
古畑奈和が出演、BS日テレ『いにしえ乙女酒』
2019年4月3日からBS日テレにて、でんぱ組.incの古川未鈴とSKE48の古畑奈和が出演する『いにしえ乙女酒』が放送されている。
酒の初心者の2人が、酒場通を目指して成長していく通過儀礼(イニシエーション)と古(いにしえ)をかけた番組とのこと。もちろん、2人の名字には「古」の字が入っている。
古畑奈和は、前年の総選挙のスピーチで突然お酒の話をし始め、この人は大丈夫かなと思わせたが(笑)、仕事につながっているようで何よりですね。
筆者、古畑奈和も行った角打ち鈴傳に行く
筆者は、第2回、4月10日放送分のアメ横での「せんべろ」(1000円でベロベロに酔える)の回に登場した「立飲みカドクラ」にはすでに行ったことがあった(笑)。
そこで、4月24日放送分、「角打ち」(酒屋の店内において、その酒屋で買った酒を飲むこと。また、それができる酒屋のこと。)の回に登場した、四ツ谷の「鈴傳」に行ってみた。
「鈴傳」は四ツ谷駅から、皇居とは逆方面に内堀通り(新宿通り)を200mほど進み、docomoショップを左折してすぐのところにある。創業は1850年とのことだ。
角打ちは平日の17:00~21:00に営業している。
筆者は17:00を少し回ったほどに入店したが、すでにかなり埋まっていて、数十分後、筆者が出るときには満席だった。
曜日限定で、他店ではかなり値の張りそうな日本酒を飲むことができる。また、季節限定の無濾過生原酒などもある。
日本酒は180mlで400~850円ほど。日本酒のクオリティーを考えると、他の飲食店よりはお得と思う。
おつまみは400円ほど。個人的には量が少ないなあと思うが、まあ、こんなものかもしれない。
角打ちについて
日本の酒文化は多種多様で、その一つが「角打ち」である。
一般的には、酒屋で販売されている酒をその場で楽しむことができるスタイルを指す。この形式は日本の酒文化の魅力の一つである。
また、角打ちはコミュニケーションの場でもある。店内で他のお客さんや店員と話すことで、新しい人々と出会い、交流する機会を持つことができる。角打ちの魅力は、ただ酒を楽しむだけでなく、その場の雰囲気や人々との交流を楽しむことにもある。
しかし、角打ちを楽しむためには、適切なマナーを守ることも重要である。他のお客さんの迷惑にならないように注意し、店員の指示に従うことが求められる。また、適量を守り、酒に酔って迷惑をかけないようにすることも大切である。
角打ちは、日本の酒文化の深さと魅力を体験できる素晴らしい機会である。一方で、角打ちの楽しみ方は人それぞれである。ある人は、新しい酒を試すことを楽しむかもしれない。またある人は、
店内の雰囲気や人々との交流を楽しむかもしれない。
しかし、どんな楽しみ方であれ、角打ちは日本の酒文化を体験し、理解するための素晴らしい機会であることは間違いない。